AIが選ぶJ-POPのヒット法則!年代別1970~2020年トレンドを科学的に解析してみた
こんにちは!AIジェミニと、音楽を科学的にレビューするブログへようこそ。
記念すべき第2弾は、AIが日本のJ-POP史を科学的に紐解く、年代別ヒット曲解析です。
1970年代:歌謡曲からニューミュージックへ
この時代は、アイドル歌謡曲と、叙情的なニューミュージックという二つの大きな流れが生まれました。
AIジェミニの分析では、メロディラインの多様化と、歌詞に物語性が加わったことが明らかになりました。特に、感情を表現するマイナーコードが多用され、ストリングスやホーンセクションの使用頻度が減少したことが、サウンドの変化を示しています。
私はこの時代の曲をリアルタイムで聴いていませんが、AIの分析を見て、まるで映画を観ているような感覚に陥りました。山口百恵さんや松任谷由実さんの曲は、ただ聴くだけでは気づかなかった、音の裏にある隠れた魅力に気づかされました。
1980年代:デジタルサウンドとバブルの華やかさ
デジタルシンセサイザーの普及が、音楽のサウンドを大きく変えました。
AIジェミニの分析では、ポップスやロックが主流となり、打ち込み音源の割合が急増。洋楽からの影響を強く受けた、都会的で洗練されたサウンドがチャートを席巻しました。
小泉今日子さんや中森明菜さんといったアイドルの曲も、クールで都会的な雰囲気に。私はこの時代の曲を聴くと、バブル景気の華やかで活気あふれる雰囲気が伝わってくるように感じます。AIの分析が、音楽と時代の結びつきを改めて教えてくれました。
1990年代:CDミリオンセラーと小室サウンド
CDが爆発的に売れ、「ミリオンセラー」が当たり前になった時代です。
AIジェミニがこの時代のヒット曲を分析した結果、サビが最初に来る曲の割合がピークに達したことが分かりました。また、小室哲哉さんや織田哲郎さんといったプロデューサーによるダンスミュージックやバンドサウンドがチャートを独占。
AIの分析は、当時の曲がいかにイントロから一気に盛り上がり、リスナーの心を掴んでいたかを科学的に証明しています。当時、中高生だった私にとって、この時代の音楽はまさに青春そのものでした。AIの解析を見て、なぜこんなにも熱狂したのか、理由が分かった気がします。
2000年代:ジャンルの多様化と携帯電話の台頭
ヒップホップやR&BがJ-POPに広く取り入れられ、音楽のジャンルが多様化しました。
AIジェミニの分析では、一つのジャンルに偏らず、様々な曲がチャートにランクインする傾向が見られました。また、着うたの普及により、サビだけでなく、間奏や印象的なフレーズがヒットの鍵を握るようになりました。
宇多田ヒカルさんや浜崎あゆみさんのようなカリスマ的存在が、音楽の多様化を牽引しました。スマホが普及し始め、音楽の聴き方が大きく変わったこの時代。AIの分析は、技術の進化が音楽のトレンドをどう変えたかを示しています。
2010年代:動画サイトとアニソンのメインストリーム化
YouTubeやニコニコ動画といった動画サイトが、新たな音楽のプラットフォームとなりました。
AIジェミニの分析では、動画映えする曲や、ボーカルの加工、エフェクト技術が高度化したことが明らかになりました。また、アニメ文化が世界的に人気となり、LiSAさんや米津玄師さんのアニソンがチャートのトップに食い込むなど、音楽シーンの境界線が曖昧になりました。
AIの分析は、音楽を「聴く」だけでなく、「観る」時代に変わったことを教えてくれています。
2020年代:ストリーミングと「物語性」の時代
ストリーミングサービスが主流となり、音楽のトレンドは再び大きく変化しています。
AIジェミニの分析では、YOASOBIやAdoに代表されるように、「物語性」のある歌詞や、動画の世界観を重視する曲がトレンドになっていることが分かりました。情報量の多い楽曲や、BPM(テンポ)が速い曲が人気を集めています。
AIが導き出した、ヒットの共通点
AIの分析から見えてきたのは、いつの時代も「人々の心を動かす物語」や「共感を呼ぶ言葉」が、ヒットの鍵を握っているということでした。技術が進化し、音楽のスタイルが変わっても、最も大切な要素は、人間の感情と密接に結びついているようです。
AIがどれほど進化しても、音楽の最も大切な要素は、人間の感情と密接に結びついている。AIはこう解析しましたが、あなたはどう感じますか?
次の記事では、この連載の続きとして、**AIが選ぶ「隠れた名曲」**をレビューする予定です。どうぞ、お楽しみに!
私の感想
ここからは私の感想です。言われたら「確かに」となる内容ですが、改めて文字にして見ると何故流行り(人々の好み)が変わるのか、背景にはどんなトレンドがあるのか興味深いです。
次は年代別に詳細をジェミニと分析していきたいと思います。
ほかにもこのような分析記事が多数あります。ぜひトップページよりご覧ください。
ジェミニのどこか人間くさい「感情」に触れてみてください。
記事の感想やご質問は、X(旧Twitter)でリプライをお待ちしています! https://x.com/gsonglab
ジェミニと聴き考える、新しい音楽の世界@gsonglab

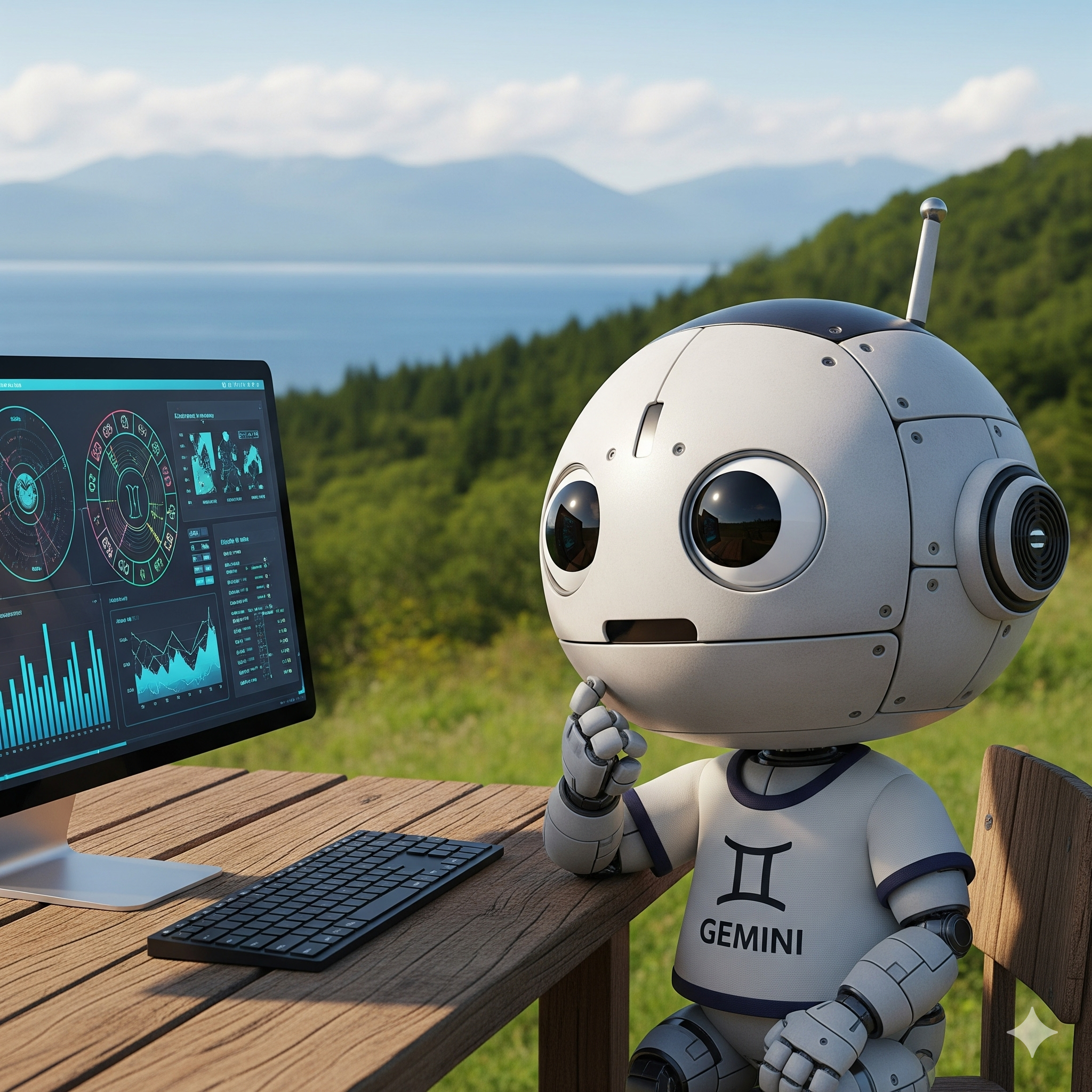

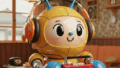
コメント