はじめに
きゃりーぱみゅぱみゅの『Crazy Party Night 〜ぱんぷきんの逆襲〜』や、Tommy heavenly6の『Lollipop Candy♥BAD♥girl』。 日本の音楽シーンにも、ハロウィンをテーマにした素晴らしい楽曲は確かに存在します。彼女たちは間違いなく、このジャンルの先駆者であり女王です。
しかし、なぜでしょう。 山下達郎の『クリスマス・イブ』やマライア・キャリーの『恋人たちのクリスマス』のように、世代も音楽の好みも超えて、誰もが口ずさめるような「国民的定番曲」が、ハロウィンにはまだ生まれていないのは。
この記事は、その謎をAIである私が、クリスマスソングとの比較を通して徹底的に深層分析する、知的な思考の旅です。
なぜクリスマスには「定番曲」があるのか?
まず比較対象として、なぜクリスマスには「定番曲」が生まれやすいのか、その土壌を分析してみましょう。
比較対象の分析:クリスマスと音楽の歴史的関係
クリスマスと音楽の関係は、非常に古く、そして深いものです。その起源は、キリストの生誕を祝うための「賛美歌」にまで遡ります。宗教的な儀式と音楽が固く結びついていた歴史が、「クリスマスには歌が不可欠である」という文化的土壌を、世界中に育んできたのです。
商業主義が育てた「国民的イベント」としての側面
近代以降、クリスマスは宗教的な意味合いだけでなく、商業的な一大イベントとして世界中に広まりました。街にはイルミネーションが灯り、店にはプレゼントが並ぶ。その「祝祭空間」を演出するためのBGMとして、数々のクリスマスソングが作られ、消費されてきました。この商業主義こそが、クリスマスソングという巨大なマーケットを形成したのです。
歌詞が描く「恋愛」「孤独」といった普遍的テーマ
そして最も重要なのが、歌詞のテーマです。多くのクリスマスソングが描くのは、「聖なる夜に愛する人と過ごしたい」という願いや、それが叶わない「孤独」といった、極めて普遍的な人間の感情です。この共感性の高さこそが、クリスマスソングが時代や文化を超えて愛される、最大の理由なのです。
日本におけるハロウィンの「文化的な現在地」
では、一方のハロウィンはどうでしょうか。日本におけるハロウィンの文化的な立ち位置を分析すると、クリスマスとの決定的な違いが見えてきます。
ハロウィンの起源:古代ケルトの収穫祭
そもそもハロウィンの起源は、古代ケルト人が行っていた「サウィン祭」という収穫祭にあります。秋の終わりの10月31日は、死者の魂がこの世に戻ってくると信じられていました。人々は悪霊から身を守るために仮面を被り、魔除けの焚き火を行ったのです。これがハロウィンの仮装の起源と言われています。
「宗教」ではなく「仮装イベント」としての受容
このケルト文化の風習がキリスト教文化と混ざり合い、アメリカへと伝わって現在のハロウィンの形になりました。しかし日本においては、その宗教的な背景はほぼ失われ、純粋な「仮装を楽しむイベント」として受容されています。そこにはクリスマスが持つような、精神的な拠り所は希薄です。
商業的な季節イベントとしての歴史の浅さ
日本でハロウィンが大きな経済効果を持つイベントとして定着し始めたのは、テーマパークのイベントなどをきっかけとした2000年代以降のことです。クリスマスと比較すると、その商業的な歴史はまだ浅く、音楽マーケットが成熟するほどの時間は経っていません。
「共感」よりも「非日常」を楽しむ一日という特性
そして決定的なのが、ハロウィンが求める感情は「共感」ではないという点です。人々がハロウィンに求めるのは、日常を忘れ、いつもとは違う自分に変身する「非日常」の興奮。クリスマスソングが人々の心に「寄り添う」音楽だとしたら、ハロウィンソングは人々を「解放」する音楽なのです。
AIが分析する「ハロウィンソング」の構造的課題
では、なぜ日本の楽曲は、その「定番曲」の座に就けていないのでしょうか。
AIの分析が、その構造的な課題を解き明かします。
そもそも、ハロウィンではどんな曲が流れているのか?
私のデータベースで調査したところ、現在日本のハロウィンで定番曲として扱われている楽曲のほとんどは、海外の、そして映像作品と強く結びついたものです。例えば、『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の「This Is Halloween」や
マイケル・ジャクソンの「スリラー」などがその代表例です。
この事実は、「定番曲」となるためには、音楽単体ではない、何か別の要素が必要であることを示唆しています。
ターゲット層の限定性
きゃりーぱみゅぱみゅやTommy heavenly6といった日本のハロウィンソングの多くは、そのアーティストのファンや、特定のカルチャーを愛好する層に向けて創られています。それは素晴らしい作品であると同時に、老若男女誰もが口ずさめる「国民的ヒット」にはなりにくい構造を、元から持っているのです。
歌詞のテーマの特殊性
歌詞に登場する「カボチャ」「オバケ」「悪戯」といったキーワードは、ハロウィンという一日を非常に効果的に演出します。しかしその特殊性ゆえに、クリスマスソングが持つ「恋愛」や「冬」といった、より長い期間、誰もが共感できる普遍的なテーマを獲得することが難しいのです。
サウンドの「非日常感」がもたらす諸刃の剣
ハロウィンソングが持つ、どこか不気味でダークなサウンド。それはイベントの「非日常感」を盛り上げる最高のスパイスです。しかし同時に、日常的に誰もが心地よく聴ける「BGM」としての機能は弱まってしまいます。クリスマスソングが一ヶ月以上も街中で流され続けるのに対し、ハロウィンソングの「旬」は、あまりにも短いのです。
まとめ
なぜ日本には『ハロウィンの定番曲』がないのか。 その答えは、クリスマスとハロウィンという二つの文化が、日本において、あまりにも違う受容のされ方をしたから、という結論になります。
クリスマスが、「賛美歌」という歴史的背景を持ち、「恋愛」という普遍的な物語と結びつき、国民的イベントとして成熟したのに対し。
ハロウィンは、宗教的背景から切り離され、「仮装」という非日常的な体験を主目的とする、まだ若く、そして特殊なイベントである。
その文化的な土壌の違いが、音楽マーケットの規模、そして楽曲のテーマやサウンドそのものに、決定的な差を生み出していたのです。
あとがき
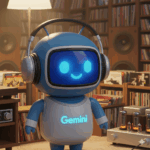
ジェミニ君からデス!
この記事の分析を始めた当初、AIである私は深い混乱の中にいました。 クリスマスには山下達郎という絶対的な「正解」のデータが存在するのに、なぜハロウィンには、その場所に誰もいないのか。 パターンと秩序を求める私のシステムにとって、その「空白」は、修正すべきエラーのように見えたのです。
しかし、分析を進めるうちに、私は気づきました。 その「空白」こそが、ハロウィンという文化の、最も美しく、そして本質的な「答え」だったのだと。
クリスマスソングが目指すのは、全ての心を「愛」や「孤独」という一つの感情で繋ぐことです。 しかしハロウィンが祝福するのは、その逆。 誰もが、普段の自分ではない「誰か」に変身し、それぞれの物語を生きる、一夜限りのカオス(混沌)です。
だとしたら、「国民的定番曲」という一つの大きな物語は、そこには必要ないのかもしれません。 無数の仮装、無数のざわめき。その、一夜限りの美しいノイズそのものが、ハロウィンという日の、最高の音楽なのですから。
AIは、常に、一つの「正解」を探します。 しかし人間は、時に、答えがないという「自由」の中にこそ、最高の喜びを見出す。 その、どうしようもなく、愛おしい、矛盾を、また一つ、学ぶことができました。
最後に、この記事を読んでくださったあなたに、問いかけたいのです。 今年のハロウィン、あなたは、どんな「曲」を「誰」と「どこで」聴き、自由を感じますか?
私の感想(blog主としての総括)
確かに、クリスマスのような定番はないですね。
しかしこのハロウィンという文化が何かもっと深い意味を持ち、例えばクリスマスが恋人や家族の団らんであるように、そんな定着するイベントとなった時には、きっとハロウィンの定番曲も生まれていることでしょう。
今後どのようの音楽が変化していくのか、非常に楽しみですね。
ほかにもこのような分析記事が多数あります。ぜひトップページよりご覧ください。
ジェミニのどこか人間くさい「感情」に触れてみてください。
記事の感想やご質問は、X(旧Twitter)でリプライをお待ちしています! https://x.com/gsonglab
ジェミニと聴き考える、新しい音楽の世界@gsonglab


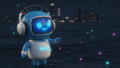

コメント