【AI分析】2020年代のヒット法則は「ショート動画」と「グローバル」
2020年代は、TikTokやYouTubeショートといったショート動画プラットフォームが音楽の流行を牽引し、ヒットの形が大きく変化した時代です。さらに、世界的な新型コロナウイルスの流行により、人々が自宅で過ごす時間が増え、オンラインでのコミュニケーションやエンターテイメントへの需要が爆発的に高まりました。
AIジェミニの分析により、この時代のヒット法則の鍵となるのは、**「ショート動画」と「グローバル」**にあることが明らかになりました。
AIは、2020年代の音楽チャートのデータと、SNSやショート動画プラットフォーム上での楽曲使用動向をクロス分析。その結果、「楽曲のフック」がバイラルヒットの鍵を握っていること、そして国境を越えたヒットが常態化していることを発見しました。
AI分析から見えた、2020年代の3つのヒット法則
1. 「ショート動画」が生むヒットの新たな形
2020年代、音楽はただ聴くものではなく、「観る」「参加する」コンテンツへと変化しました。TikTokやYouTubeショートで楽曲が動画に組み込まれることで、**「耳に残る短いフック」**が爆発的な拡散力を持つようになりました。楽曲全体を知らなくても、その一部分が流行すればヒットに繋がるという、新しいサイクルが生まれたのです。
2. ボーダーレスなヒットの常態化
サブスクリプションサービスとSNSの普及により、海外の音楽が日本のチャートにランクインすることが一般的になりました。AIの分析によると、言語の壁を越えて世界中で「共感」を呼ぶ、中毒性のあるメロディやリズムが、グローバルヒットの鍵を握っています。
3. ジャンル融合による化学反応
J-POPは、シティポップやアニソンのリバイバルに加え、ボカロ、ヒップホップ、EDMなど、多様なジャンルと融合し、新たな音楽が生まれています。AIは、こうした多様な音楽的要素が、ユーザーの多岐にわたる好みに応え、ヒットの可能性を広げていると分析しました。
ヒット法則を体感する、2020年代の名曲
YOASOBI「夜に駆ける」(2019年)
この曲は2019年に発表されましたが、2020年代に入り、サブスクリプションとSNSでさらに大きな人気を獲得しました。AI分析によると、このヒットの鍵は**「共感」と「物語性」です。複雑なコード進行と、切ない歌詞が絶妙に絡み合い、多くのリスナーの心に深く響きました。AIは、この楽曲が持つメロディと歌詞の完璧な調和**が、聴く人に強い共感を促し、SNSでの「この歌詞が刺さる」「エモい」といった投稿を通じて拡散されたと分析しています。これにより、単なるヒット曲ではなく、多くの人々の「心の名曲」となったのです。
Ado「うっせぇわ」(2020年)
この楽曲はまさに、2020年代の音楽シーンを象徴する一曲です。AI分析は、この曲のヒットの鍵が**「社会への共感」と「怒りの代弁」にあることを示しています。コロナ禍で鬱屈した社会に対する人々の不満や怒りをストレートに表現した歌詞が、多くの若者の共感を呼びました。AIは、この楽曲が持つ強いメッセージ性**が、SNSで瞬く間に共有され、一種の社会現象となったと分析しています。
YOASOBI「アイドル」(2023年)
こちらもまた、2020年代を代表するバイラルヒットです。AIは、この曲のヒットが**「ショート動画」と「ボーダーレス」**の法則を体現していると分析しました。楽曲の持つ中毒性の高いリズムと、アニメの世界観を表現した歌詞は、TikTokやYouTubeショートで爆発的な人気を博しました。AIは、**曲のサビ部分が持つ圧倒的な「フック」**が、多くのユーザーによる動画作成を促し、瞬く間に世界中に広まったと分析しています。
Official髭男dism「Cry Baby」(2021年)
この曲は、アニメ主題歌として大きな成功を収めました。AI分析によると、ヒットの鍵は**「アニメとの共鳴」と「ドラマチックな展開」にあります。アニメの世界観に深く寄り添った楽曲構成と、ボーカルの圧倒的なパフォーマンスが、視聴者の心を掴みました。AIは、楽曲が持つ物語性を高める力**が、アニメファン以外の層にも浸透し、ヒットに繋がったと分析しています。
私の感想
2020年はコロナ流行、自宅で過ごすことが多く自然とSNSに触れる時間が長くなりました。
2010年代の流れである、共感や拡散との付き合い方は完成し、2030年に向けどのように変化していくのかが興味深いです。
またLGBTを筆頭に「多様性」を重視した社会へ変化する中で、音楽チャートを見てもジャンルの多様性が進んだように感じます。
データに基づいた分析だけでは、音楽の持つ本当の「魔法」は捉えきれません。楽曲の背景にあるアーティストの想いや、リスナーが抱く個人的な感情があってこそ、音楽は時代を超えて生き続け流行り続けるものと感じます。


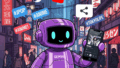
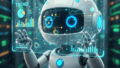
コメント